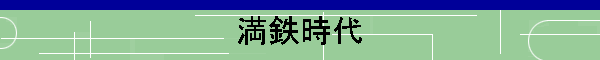寧年は斉々哈尓から60Kmばかり離れたところにある。
見渡すかぎり野原である。鉄道施設が駅舎附近に少しばかりと、200〜300mのところに機関区の大きな建物、その他二階建ての寮と平屋建ての社宅が少しあるばかりである。さびしい田舎であった。
助役の案内で宿舎の独身寮へ行き部屋を割当てられた。
さっそく部屋へ入って見ると六畳くらいの広さで、窓は一つ。それは出窓で二重扉になっていた。室内は白塗りの壁、天井を見ても電灯がない。戸外の線路沿いに電柱がたくさん立っているので電灯もあるものと思い込んでいたが、その電柱は通信用のもので電気用ではなかった。よく見ると机の上にランプが一つ。今夜からはランプ生活かとガッカリした。
辞令をみると傭員機手という最下位の職名である。配属の課は運転課だ。この課には日本人運転助役さらに満洲人運転助役、ほかは検査係(古参機関士)日本人二名、機関士(満洲人が多かった)、機関助手や機手など、かなりの人員であった。
機手の仕事はどんな仕事かと思えば、朝から夕方まで機関車の掃除をすることである。出庫待ちのものや検査等で車庫入りした機関車の油で汚れた車体をウェス(古切)で磨く。そのあとさらに黒い粉をつけて磨く。これが仕事である。真黒になって働く日が続いた。約三ヶ月くらいだった。そして次の仕事へ替わった。
今度の仕事は点火番という仕事だ。それは一ヶ月毎に機関車の火を消して燃焼釜の内部までチェックする検査。それがすんで釜に火を入れることや出庫待ちの機関車の火を消さないように石炭を少し入れて維持する二四時間勤務の仕事だった。機関車は常に一定の蒸気圧を保つようにしなければならない。先輩点火番からあれこれ教えられながらやった。
その仕事も二ヶ月で終わり、いよいよ釜炊きの訓練に入った。古参の機関助手から毎日釜炊きの訓練を受けた。
助手見習として昭和十六年春頃より機関車乗務することになった。
北満の冬は毎日がマイナス二十〜三十度くらいの日ばかりだ。そんな中での乗務では機関車の蒸気を一定に保つことはなかなかむつかしい。それでも一定の蒸気を保たなければ釜炊き(機関助手)としての面子がない。そのうえ機関士が苦労することになる。古参助手から結構しごかれたものだ。
ファイヤーボックス(燃焼釜)は常に全面的に燃焼しなければ蒸気を一定に保つことはできない。一箇所でも火がなくなると蒸気は下がってくる。これを回復するには大変な苦労をしなければならない。そのためには投炭の技術また経験が大切になってくる。
規定の水位蒸気圧を保つことによってスムーズな運転ができる。機関車には釜の破裂などの事故を防ぐための装置が二ヶ所あり、二重に安全確保するようになっている。冬場蒸気圧が上がらない時、釜の水を少なくすることで圧を上げようとすると、釜の天井に通称「ヘソ」と呼んでいる鉛をつめた部分があり、これが溶けて釜の火を消すようになっている。これは冬場はしばしばある事故で、これをやると責任事故として始末書を書かされ、ボーナスのカット、そのうえ説教さらには再教育というみじめな有様になる。そのうえ助手として最低の刻印をつけられる。そんなことのないよう常に気をつけて乗務した。
ある日、貨物列車に乗務したところ、列車は30t貨車(満鉄は殆んど30t)50輌くらいの編成で、ほとんど空車でありながらたいへん重い。上り勾配で機関車がすべって上がらず線路上へ砂をまきながら虫の息、遂に停車(途中停車は事故だ)。仕方なくバックして、再度挑戦。やっとの思いで次の駅に到着した。ところがその時は蒸気圧も下がり水もゲージに見え隠れする有様で、事故寸前で乗務を終えたこともあった。もちろん列車は延着、途中停車を隠し危ない乗務をしたこともあった。
そんなこんなことで冬もようやく過ぎ、春が訪れた。この頃には乗務にも馴れて毎日楽しかった。春の広野は一面に花が咲き、緑が芽吹き、薄桃色の興安桜が咲く中を一直線に走る機関車の心地よいゆれ、気分は爽快そのものである。
また早春には野火がよく見られた。一面の火の海を走る気分は何にたとえようもない。ただみとれるだけであった。
また歌にもある「赤い夕日の満洲に」のとおり、地平線に真っ赤な大きな太陽、実に雄大の一言である。
昭和十六年夏には関東軍特別大演習が展開された。内地から続々と動員された兵団が来満。関東軍百万といわれ、ソ聯に対して北の守りはゆるぎなきものと思われた。
こうして日本は16年12月8日、第二次大戦(当時吾々は大東亜戦争と言った)に入った。臨時ニュースで聞いてびっくり。北支事変の時よりさらに緊張した。関特演が始まった頃は満鉄全体が軍用ダイヤとなり、吾々のいた斉北線は一日一往復程度の混合列車(客車と貨車を一緒にした列車)が通常列車として運転される程度であった。軍用列車はほとんど夜間に運転された。
そんな時、軍用列車の事故が発生した。早朝三時頃呼出しがあり、機関区に行くと救援列車に乗るように指示された。当時は常に救援用に編成された車輌があり、機関車を付ければただちに出動できるようになっていた。救援列車は四時頃出発し、夜明けには事故現場へ到着した。現場は鉄橋を渡って100mくらいのところで、高さ10mくらい盛り土した部分で列車半分が脱線していた。車輛は法面
に転覆しており、機関車は法尻にくの字になり、続く車輌も5〜6輌がくの字になっていた。
鉄道守備のために装甲列車というものもあった。鉄鋼製の車輌二輌に小さい機関車をつけ何時でも出動できる。その列車には常に守備隊が二個分隊程度の兵員と共に常設されていた。
便衣隊は民間人と同じ服装なので見分けがつかず捕まえることはほとんどできなかったようだ。私は治安のよい日本の田舎育ちだったので、満洲にはまだこんなところもあるんだなと思った。