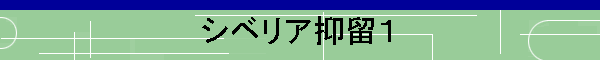昭和二十年九月十二日、研修所に入った吾々はソ連軍によって一大隊千名単位に分けられ、奉天駅の引込み線へと次々と連行(日本軍の編成等は無視、員数のみの編成)された。その日も暑い日和であった。周囲を見れば見知らぬ兵もたくさんおり、召集兵らしき年齢の者もいた。また、初年兵らしき若い兵もいた。お互いに話もなく、自分のことを思い、それぞれ荷物を持って黙々と列車の場所へと行進する。私もとりあえず着の身着のまま、少量の甘味品(ラクガン)と飯盒に水筒くらいで身軽い状態で列に加わった。なかには召集兵と思われる兵で、大きな荷物を負えるだけ負って汗を流しながら歩く者もいた。
吾々が唯々諾々とソ聯の指示に従ったのは、「日本へ帰れる」という話を信じたからだ。それはもちろん確実な情報ではない。しかし、ソ聯兵の「トウキョウダモイ」(日本へ帰る)という言葉に一縷の望みをかけた。
私は司令部にいたので司令部の者と一緒に満鉄の寝台車に乗せられた。車輌には各百名が乗せられた。車輌の出口へ一人ずつマンドリン(小型の自動小銃)を持ったソ聯兵が乗っていた。そして朝夕必ず人員点呼をする。ところがこの兵隊、数を百までなかなか数えられない。一方から一、二、三とかぞえ始めるが途中で動いたらまた初めからやり直す。何時までたっても終わらない。そのうち腹を立てて車輌の外へ全員出して一人ずつ車輌へ入れ、やっと百となり点呼が終わる。
列車が走行中は暇なので、日本兵の腕時計や万年筆をあさり、見つけると取り上げる。時計は必ず耳にあて音を確かめ、音のしないのは取らない。両腕に二〜三個ずつは持っている。なかには翌日になるとネジが切れて音がしないと持ってきて返すのもいた。当時の時計はネジ巻なので一日もすれば止まるのは当然。まったく程度の低さには驚いた。
ソ聯邦時代は十数ヶ国の聯邦制なので教育も程度が低い。また、統制経済の為、生活必需品以外はほとんどなく、時計などは国民のほとんどが持っていなかった。万年筆もなく、すべて付けペンだった。
私たちの車輌にソ聯軍の輸送指揮官(若い中尉)がよく出入りした。その指揮官に吾々を何処へ連れて行くのかと問うと、哈尓浜までの命令は受けているがそれから先はわからないと言う。日本人にはこんな小出しの命令はどうも理解できない。まったく秘密主義というかあきれたものだ。
満洲輸送中は米はなく、わずかに配給してくれるのは粟、それも皮付きである。粟飯は知っていたが、炊き方はわからなかった。ある小さな駅で停車した。炊飯だ。さっそくそこらの野原へ水溜りを探しに行き、燃料も枯草を拾って飯盒炊飯をする。もちろん水加減もわからない。最初は硬い粟飯だ。残りにまた水を入れて炊き、二〜三回でようやく粟粥となってくる。
こんな状況が数日続いた九月下旬、ある小さな駅で停車した。駅舎附近を見ると、五〜六歳の男の子と小さな子を背にした母親がいつ乗れるかわからない汽車を待っている姿が目に入った(おそらく開拓団の者と思われる)。見れば男の子は素足に着物姿である。北満の九月下旬は、朝夕ともなればもう零度以下になる。そんな中で行くあてもなく路頭に迷っている。その親子を見て同胞として、いや軍隊として守るべきことができないいらだたしさに情けなく涙する思いだった。フト気付いて自分の持っていた甘味品(ラクガン)を雑嚢から出して子供の手に渡してやった。無事に故郷へ帰れることを祈る。母親らしき夫人は涙を流して喜んだ。
また孫呉
近くの小さな駅に停車。そこでは二〜三時間の余裕があった。炊事洗濯等をするため周りの野原に水を求めて歩き回った。やっと草原の中に水溜りを見つけた。皆が我先にと集まってくる。生い茂る夏草を分けてできるだけきれいな水をと思って入ったが、よく見るとボーフラが浮いている。そこで一計、水面を叩くとボーフラが沈む。すかさず水を汲む。その水で粟飯を炊いた。
周りをよく見ると洗濯する者、用便をする者、さまざまである。さらに先の方を見ればなんと死体が浮いているではないか。よく見れば二〜三体、それも日本兵である。惨めな姿だ。この附近の戦闘がかなり激しかったものと思われる。どうすることもできずにその場を去る外はなかった。
九月も終わる頃、ようやく黒河
の駅についた。そして収容所らしきところへ入った。ここに三〜四日滞在する。その間、ソ聯軍の命令で毎日略奪品の船積に使役された。たまたま私たちは麻袋に入った麦を船に積まされた。一袋約一〇〇kgあり、これを担がされて、アユミイタ歩板の上を歩いて船に積む。馴れないことと重いのにあえぐ有様。ソ聯兵の罵声に腹は立つやら情ないやら、こんな奴らにとの思いだった。