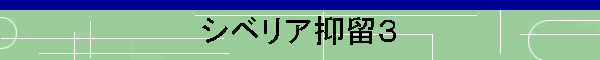| シベリア |
ウラル山脈から太平洋岸まで、東西七千km、面積一千万平方km。日本のざっと二十七倍の広さだ。ここに五十七万五千人の日本人捕虜がばらまかれ、五万五千人が死んだ。満洲事変に始まる十五年戦争が戦後にもたらした永い永い悲劇だった。
ソ聯は第二次世界大戦の戦勝国ではあったが、ドイツとの戦いで広大な地域を占領され、そこからドイツ兵を追い払い、ドイツ軍に決定的打撃を与えるために国力のほとんどを注いだ。そして返ってきた土地は戦火で荒廃したところ。勝利の代償は疲弊と窮乏のどん底生活だった。そうしたソ聯の復興のため日本人、ドイツ人捕虜が酷使されたのだ。
入ソ輸送施設、医療の不備とあいまって入ソ途中ですでにかなりの患者、死亡者を出した。ソ聯の収容所は居住施設の多くが粗悪で、その中に多数の人員を収容し、暖房設備や燃料も不十分のままマイナス三〇〜四〇度の越冬生活を強いた。加えて衣類は着用したもののみで十分な防寒装具はなく、さらに食料は量、質ともにはなはだしく不足、健康を維持する最小限のカロリーの摂取さえできない状況であった。あちこちの部隊から集めた者ばかりだから、戦友の名前等知ることもなかった。誰が何処で死んだかまったく不明のままであった。
マイナス四五度の吹雪では睫が凍り、瞬きすると音をたてる寒さである。こんな時には体力のないものは睡魔におそわれてそのまま眠って凍死する。こんなことがあちこちの収容所でいくらでもあった。しもやけに罹ったなと感じた時には凍傷が第三期まで進んでいて、吊るし柿のようになって腐った指の肉の間から骨が飛び出す。シベリアの寒さは口で言い表すことのできない寒さである。
凍傷で死んだものもたくさんいた。足の指を切り落とす。医療品の不足、体力の低下で雑菌におかされ化膿する。次は足首まで切断、そしてさらに膝も切断。ここまでくるともはや死のみである。
シベリアの寒さは吾々捕虜にとっては一歩踏み誤ると死につながる。四六時中死と背中合わせである。
またこんな現象もあった。"銀粉が舞う"のである。日本では見ることもできない現象だ。晴天になると太陽熱で雪の表面が解ける。水蒸気になる。それが地上二〜三mのところでパッと凍る。その結晶がまた太陽熱で一瞬に砕ける。それが銀粉となって舞う。太陽に照らされキラキラ光る。不思議な美しい眺めである。こんな時は寒いというより痛い。息苦しい。それは空気が凍っているからだ。
風速一mを気温一度と換算して、気温がマイナス三〇度で風が一〇mあれば体感気温はマイナス四〇度となる。吾々の収容所では気温マイナス三〇度で風速五mとなると作業は中止して収容所へ帰ることになっていたが、こんなことで帰ることはほとんどなかった。
|
| 尾篭な話を一つ |
ソ聯の便所について。冬では氷点下三〇度〜四〇度は毎日のことだ。こんな中で巾一五〜二〇mほどの穴を掘って板切れを渡したのがシベリアのトイレである。用を足すと落ちるそばから凍りつき、それが盛り上がってすぐに板切れの間から顔を出すようになる。夜中なんか電気もなくまっ暗である。しゃがんだとたんに尻を突き上げられる。
そこでこの塔を壊す作業が私たちに課せられる。ツルハシで壊すが、作業中小さいかけらが服につき、そのまま暖房のきいた部屋に帰るとそれが解ける。室内はものすごく臭い。こんななかでもみな何も言う者はいない。人間じゃなかった。
|
| 入ソ当時 |
入ソ当時は満洲から積んできた粟を食べ、毎日粟粥とスープだけであった。黒パンはあまり支給されなかった。そのために体力が落ちる。寒さと空腹と絶望の中、ひたすら生きることを考えるだけであった。
常に飯盒とスプーンは身につけている捕虜の群れであった。
作業場への行き帰りの途中、みな下を向いて歩く。路上に煉瓦のかけらが落ちていると黒パンに見え、馬糞が落ちていると馬鈴薯に見える。
食料倉庫の荷役に行けば先ず盗むことを考える。
軍服のズボンは下が細くなっている。巻脚絆を巻くためだ。だから盗んだものはみな股の内側に入れる。ソ聯兵の検査は側面を手で触ってみるだけなので、内股に入れると見つからない。そこで細長い袋を作って、それに大麦などを入れてズボンの中隠して帰る。それを収容所のペーチカの焚き口に入れて煮て食べるのである。一回に盗む量は二、三合程度なもので大量とはいかない。
その作業場でこんなことがあった。それは百kg麻袋に麦を詰めてそれを十三個ずつ積重ねて並べていく。これを一日中やって五時に終わると、その日の出来高を計算する。見ると監督がベニヤ板の三〇〜四〇cm角のものを持ってきて、それに十三,十三,十三……と書いている。加算でやっている。それもものすごくスローペースだ。私は十三個が何列あるかを見て乗算をしてみせ、いくらだと言うと彼は驚いて
「お前は頭がいい。将校じゃないか」
と言うので、皆で大笑いをした。一般労働者はみなこの程度のものばかりであった。
|
| シラミの大群 |
酷寒の中で垢にまみれ飢えに苦しむ捕虜はまた虱の大群にも苦しめられた。肌着の縫目に一列縦隊に並んでいる。これを親指でつぶしていく。ピチピチと音をたててつぶれる。翌日の晩に見るとまた同じように一列縦隊に並んでいる。どうやら頭が残っていれば再生するようだ。昼間は体がかゆい。こんな毎日が続く。体力のないのに虱まで養ってさらに体力が落ちる。
さらに収容所内にはもう一つの敵がいた。それは南京虫だ。
寝台に寝ていると天井を夜な夜なはいまわる南京虫の大群。これが顔の上に来ると突然に落下する。一日の労働で疲れきって眠っていると首のまわりを我がもの顔で血を吸う。気がついた時にはかなり食いあと痕があり、それがひどくかゆい。あげくにキズとなり、ひどいものは化膿してしまう。昼間は作業でしごかれ、夜はシラミ、南京虫の大軍に攻められて体力は落ちるばかりであった。
シラミの駆除対策は入浴と同時に熱滅菌によって一段落つく。夜間、収容所内の巡視に来るソ聯の衛生係の将校にシラミ取りの状況を見せると、即入浴と減菌となり、一晩中全員が入浴となる。
一方、南京虫となると日曜の仕事だ。鉄の寝台は広場に火を焚いて、二人がかりで両方から寝台を持って焼いて殺虫する。木製寝台となるとそうはいかないので、大きな釜に湯を沸かしてヤカンに入れ、これを寝台の継目等にかける。これが大変手間がかかる仕事で、せっかくの休日もこんなことで「オジャン」になったものだ。
|
| 身体検査 |
身体検査(カテゴリー)は毎月行われた。ソ聯の女軍医が(中尉くらい)検査官である。一人ひとり真っ裸にされ一糸まとわず女軍医の前に行くと先ず胸の肉をつまむ。次に一八〇度まわれと言われ、後から尻の肉をつまんでみる。妙なことをすると初めは笑ったものだ。こんなことで健康状態がわかるのだろうかとあやしんだ。とどのつまりはどの程度の労働に耐えられるかの選別というわけであった。
胸や尻の肉の張りがよい者から順に一級、二級、三級、四級と言い渡される。一、二級(アジー、ドヴー)となると重労働に出される。三級(トゥリー)はラーゲル内の作業(炊事場、洗濯場、食品受領といった作業)、四級(オッカー)はすっかり肉の落ちた者で作業免除となる。私はいつも一〜二級で毎日作業に出された。
ある月の検査の時、フンドシをしていたら女軍医、顔色を変えて
「お前は病気か(ティ、ポルノイ)」
と言いながら心配顔であった。どうやらフンドシをご存知なかった様子。日本の軍隊では皆フンドシをしていたのだ。ソ聯ではこんな習慣はない。とうぜんこんなものは支給されるはずもない。それにどんな事情があろうと女の前に真っ裸で立つなんてことは日本人にはできない。だが彼女(軍医)はいっこうに平気な顔で、ふつうに話もする。
|
| 黒パンの分配 |
黒パンの分配は大変であった。一班に人数分のパンを配給し、それを三五〇gずつに分ける。これが大変なことで誰もすすんで切ろうとしない。しかたなく順番に切ることにしたが、年次の若い兵隊はとくに嫌った。古年兵があれこれと文句を言うからである。軍隊当時は威張っていた下士官あたりがそれにさらに文句をつける、小さいとか大きいとか口やかましい。毎朝七時頃にこの行事がおこなわれる。十数名の目がパンに集中。その目の鋭いこと。あの光景は仏教でいう餓鬼道の姿である。
三五〇gに分配が終わると、自分自分に寝台に座って、その場で食べるもの、三つくらいに分けて三食分とするもの、まったく手をつけずに作業場まで持ってゆき昼に食べるものと、各人各様である。どうしたら一日の飢えをしのぐか工夫していたのである。
極東シベリアの「ピロビジャン」のラーゲルでは自分のシャツをめくって虱を食べたという話もあった。
|
| 野菜採り |
寒い冬の間、捕虜はビタミン不足となってヒョロヒョロしている。自然と身体が要求するのだろう、青い野菜が食べたい。しかし、吾々の給与はカルトーシカ(馬鈴薯)とキャベツと青いトマトを漬けたものを入れた塩のスープとカーシャ(粥)だけ。それもカーシャは飯盒の蓋に八合目。傾けると流れ出るほどの薄い。スープも飯盒に半分、キャベツの三cm角程のものが一枚か二枚、トマトの切れはし、馬鈴薯の切れはしが入っていたらオンの字。これではビタミンなどまったく不足である。
野菜が出るのはやはり六月に入ってからだ。作業場の昼休みにまわりを探す。オーバコ、スギナ、アカザなど、そのほかにたまにカラシ葉に似た草。これは一株で一回食べるのにちょうどよい大きさである。見たこともない名も知らぬ草はさすがに食べる気にはなれなかった。何といってもオーバコ、スギナ、アカザはよく採ってゆがいて岩塩をつけて食べた。それでも吾々には御馳走であった。
ある時、同室の者が大声で笑い大暴れするので、皆で押え付け寝台にしばりつけて軍医を呼んだ。処置を頼んだが、軍医とて原因不明の病人、どうすることもできなかった。後日、本人回復後、カラシ葉に似た草を食べたことが判明。その野草は毒になるということで、野草は食べることを禁じられた。オーバコ、スギナ、アカザなどは漢方薬にあることを知っていたので、隠れてコッソリと食べていた。
|
| 食器・スプーン作り |
入ソ当時、食器は自分が持ってきた飯盒であった。これは一時も身体から離したことのないものである。スプーンはソ聯から支給された。これは木製で、日本のオタマジャクシのような格好の大きなものであった。当初こんなスプーンなど使われるかとばかりハシを使おうとした。しかし、カーシャ、スープではハシの出番はまったくない。なんとしても日本並みのよいスプーンをと考えたが手には入らない。
一九四五年も暮れて四六年に入って夏頃からか、作業現場からアルミ線等を盗んでは、元鋳物工などを集めて鋳型を作ってアルミのドンブリを作り始めた。しかし、なにぶん千人分(一人に二個宛)二千個のドンブリを作るとなると相当なアルミ腺を盗んで帰らねばならない。盗むことは作業現場ではうるさく言われたが、収容所内では見て見ぬ振りであった。四、五百個のドンブリができてからは所内の朝夕の食事は飯盒が不要となった。
スプーンは個人個人で作った。アルミの延板で三〜五cm巾で長さ三〇〜五〇cm、厚さは三〜五mmくらいのものを盗んだ。何に使われるものかは判らなかった。発電所などのヒューズという話もあった。(こんな材料はすべて戦利品であった。)それを切って、鉄道で使うレールの繋ぎ目のボルト(の頭)をもってアルミの延板を叩くとスプーン形となる。それをヤスリで整形して出来上がり。柄の部分には花などの模様を線彫りする。紙ヤスリで表面を仕上げるとちょっとした製品が出来上がる。
一個作り、二個作るうちにだんだんと上手になり、形もよくなってきた。街のロシヤ人もやはり木製のスプーンを使っていた。私らがアルミのスプーンを使ったり持っていると欲しがって、
「そのスプーンを売れ」
という。こちらとしても金は欲しい。また作ることを考えると、材料の調達が必要だし、手間もかかる、また休みの日に収容所の職員の目を盗んで作らねばならない。だが、なんとかしてアルミ板を盗んで休日にはもっぱらスプーン作りに精出した。一本一〇ルーブルくらいでは売れるので、何本も売ってタバコ(マホルカといってタバコの木や葉を刻んで乾燥したもの)を買って吸ったり、パンやペロシキ(メリケン粉を練って焼いた一〇cm巾の二〇cm長さのもの)を買って飢えをしのいだ。
そしてだんだんと状況がわかってきたので指輪も作って売った。材料は水道の蛇口のナットである。これを盗んで、中のネジ山を丸ヤスリで落し、六角の一辺を残して作る。真鍮かホウキン砲金なので磨けば金色となる。金の指輪だといってよい値段で売れた。
すべての物は手作りするしかない。支給されるものはほとんどないからだ。無からの出発である。生きるためには自分の全知全能をしぼって事に処するしかなかった。これができないと惨めな姿となる。
|
| 靴下 |
ソ聯に入って支給されたのは靴下(巾三〇cm、長さ七〇〜八〇cm程度の布二枚)だ。ただの布切れ二枚、これが靴下だ。どうすれば靴下となるか戸惑った。我々は軍隊当時の軍足をはいていたので、当分は手ぬぐいがわりに使っていた。またフンドシとしても使った。
ある時、作業所で監視兵が靴(半長靴)を脱いでその巻靴下を直しているのを見た。それでやっとこの布靴下の使い方がわかったが、吾々はどうしてもうまく巻けなかった記憶がある。
|
| ゴミ捨場の清掃 |
こんなことはみな日本人捕虜の仕事で、ドイツ人はこんな仕事をしていなかったと思う。やはり白色人種と黄色人種は差別があったようだ。またソ聯もドイツ人には一目おいていたと思われる。
一九四六年(昭和二十一年)二〜三月頃、このゴミ捨場の清掃に行かされた。見ると石炭の灰やゴミ、野菜のクズ、雑巾水といろいろのものが重なり合って山となっている。雑巾水を捨てたのが凍ってどんどんと山が高くなっていく。この山をツルハシで掘り起こしてトラックで運搬する。その掘り方が我々捕虜の仕事だ。
石炭灰の中によく馬鈴薯の一〜二cmくらいのものが入っていた。それを一つ一つ取り出して袋に詰めて持ち帰る。収容所内で針金に通してペーチカでこっそり焼いて食べる。これは夜中に皆が寝静まってからでないとできない。小さい馬鈴薯なのでウッカリすると焼けて炭になり食べることはできない。
これがこの作業での唯一の楽しみであった。作業に行った者が皆こんな事をするので、一人で持ち帰る数量たるやせいぜい一〇個前後。それでも皆目の色を変えて我先にと拾った。
こんな姿をソ聯の市民はどう見ただろうか?
|
| カラス・ヘビを料理 |
冬の寒い朝、ブリザードの吹きすさぶ中を作業場へ追いたてられる。行先は今日も穴掘り(水道工事)。巾八〇cm、深さ三mまで掘る。ここまで掘り下げないと水道管を敷設できない。測ったように凍っている。三mで凍っていない土が出る。水道工事は必ず冬季にする。夏季は凍土が解けて穴掘りができない。硬い凍土を掘る作業はつらい。一日三回くらいツルハシを替えないと先端が丸くなり掘ることができない。
そんな作業場に着くと先ず穴の中に目当てのカラスが落ちていないか探す。それは夜のブリザードで飛ぶことができず物に衝突して落ち凍死したものだ。多い日には二〜三羽も落ちている。さっそく他の者に見られないように羽を取って袋の中へ入れ、夕方持ち帰る。さっそくラーゲルの炊事場で焼いて岩塩をつけて食べる。焼き鳥だ。大馳走であった。
夏の電柱建設の作業。五〇m間隔に一人ずつ配置されて穴掘りをする。この穴の深さは一m五〇cmくらい。この穴へ蛇が入って来る。これをねらって電柱を建てるまでに見てまわる。見つけ次第その場で皮をはいで天日に干す。それを持ち帰り、炊事場で焼いてこれも岩塩をつけて食べる。あの頃は本当に美味しいものであった。 |